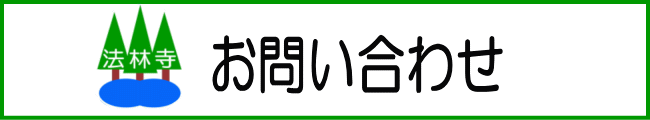「火の車」は家計ではなく自分の心の困窮
現在では、家計の困窮した状況を「火の車」と喩(たと)えますが、本来の意味は少し違います。
江戸時代の怪談話しでは、悪人が死ぬと地獄の獄卒(ごくそつ)が火の車で迎えに来ると言われます。
この「火の車」は、仏教から来た言葉だとも言われています。
お釈迦さまの教えである法華経には、「三車火宅の喩(たと)え」という教えがあります。
私たちの世間は、炎に包まれた家のようなものだと喩えられています。これを「火宅」(かたく)といい、苦しみに満ちている世界を表現しています。
そのように危険な状態なのに、私たちはのんきに楽しく暮らしているのです。
ある時、猛火に包まれ今にも崩れ落ちそうな家の中で、楽しそうに遊んでいる子供たちを長者が発見しました。
長者はなんとか、その子供たちを救いたいと思いました。
しかし突然、家が火事だと言ってしまうと、子供たちはパニックになってしまうかもしれないと考えました。
そこで、長者は方便を使い、家の外におまえたちが欲しがっていた「羊車(おうしゃ)、鹿車(ろくしゃ)、牛車(ぎっしゃ)」の三車が門の外にあるから早く出ておいでと言いました。
子供たちは、新しいおもちゃがもらえると思い一目散に「火の家」から飛び出してきたのです。
しかし、門の外には一台も車がありません。子供たちは長者に「嘘つき」といいました。
長者は家を見なさいと指さすと、猛火に燃える家があり、子供たちは救われたことに気づきました。
子供たちの安心した姿をみた長者は、その後大きな白い牛車を子供たちに与えました。
・地獄の獄卒=死者に苦しみを与える下役人。頭が牛や馬で鬼のような姿をしている。
・方便=方便とは、人を助けるために使うて手立てで嘘とは違う。「嘘も方便」という使い方は間違い
・長者はお釈迦さま、子供たちは私たち衆生の喩え
・大白牛車とは、すべての人が仏になれる教えの喩え
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
法林寺サイトにご訪問いただき、
ありがとうございました。
法林寺では、通夜葬儀の法要
からご祈願や年回忌供養など
を承っております。
経済的なご心配で、大切な方を
お見送りできないことは
とても悲しいことです。
お気兼ねなく相談ください。
あなたによりそう法林寺
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()